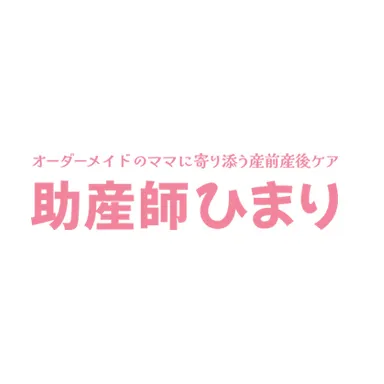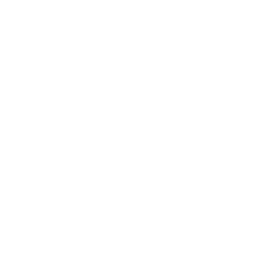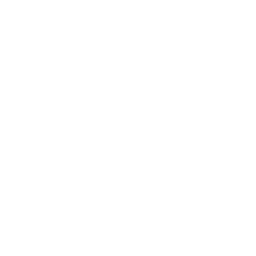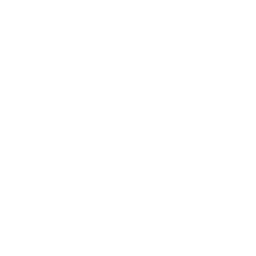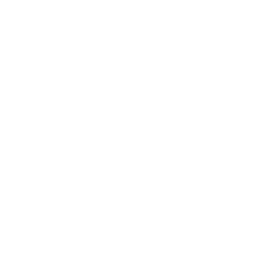乳腺炎を予防するには?前兆・授乳姿勢・授乳リズムを助産師が解説
はじめに「胸がチクチクする」「授乳のたびにおっぱいが熱い」──
そんな小さな変化を感じていませんか?
乳腺炎は授乳中のママに突然起こるトラブルの一つ。発熱や痛みによって授乳ができなくなり、育児や生活に大きな影響を与えます。
この記事では、助産師として多くのママを支えてきた経験から、**乳腺炎がなぜ起こるのか?どうすれば予防できるのか?**を徹底解説。さらに、授乳姿勢の工夫・赤ちゃんの授乳リズム作り・漢方の活用法まで幅広く紹介します。
乳腺炎は「昨日まで元気に授乳していたのに、突然胸が赤く腫れて高熱が出る」こともある急なトラブル。
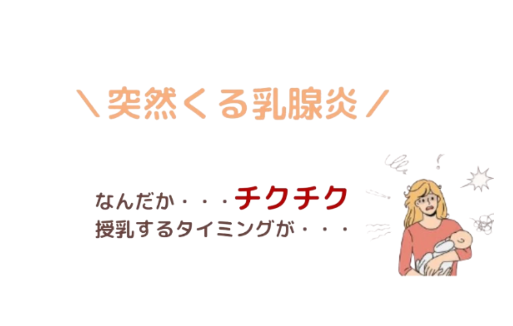
- しこりが取れない
- 授乳時の痛み
- 胸の一部が赤く熱を持つ
- こうした前兆を見逃すと一気に悪化します。
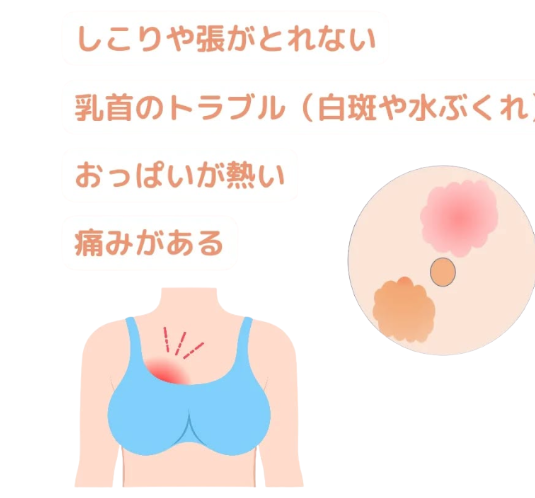
不安の具体化
「少し張っているけど大丈夫かな?」と放置してしまうママは少なくありません。
しかし、乳腺炎を悪化させると…
- 38℃以上の発熱
- 悪寒・頭痛・関節痛
- 授乳困難
- 膿が溜まる化膿性乳腺炎
体力が戻りきらない産後にこれが重なると、心身ともに大きなダメージになります。
|解決策
前兆サインを見逃さない
- 張りやしこりがとれない
- 白斑や水ぶくれ
- 胸の熱感
- 授乳の痛み
原因は母乳の滞り
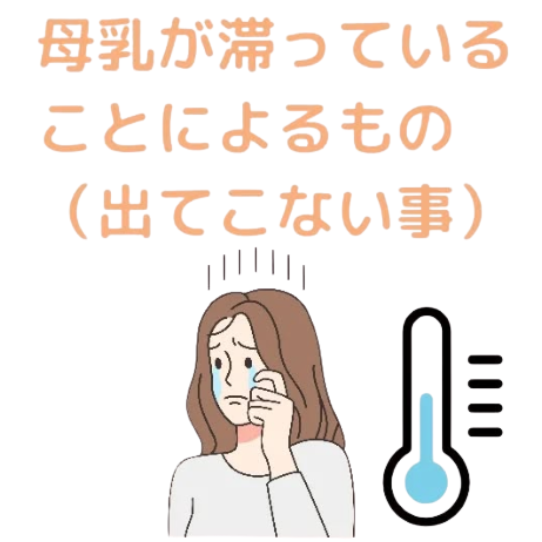
- 授乳間隔が空きすぎる
- 吸い方が浅い
- 同じ抱き方ばかり
- 水分不足
- 冷えや疲労
セルフケアの基本
- 赤ちゃんにたくさん吸ってもらう
- 多方向から授乳
- 水分をこまめに摂取(目安1日2ℓ)
- 身体を温める
- 授乳以外は休む

授乳姿勢と乳腺炎予防
横抱き
最も基本的な姿勢で、胸の中央〜外側の乳腺がよく開通します。

フットボール抱き(脇抱き)
脇の下や外側の乳腺に効果的。帝王切開後や双子育児にもおすすめ。

縦抱き
赤ちゃんの顎をしこりのある方向に向けると効果的。上下の乳腺までよく使えます。

👉 ポイント:授乳姿勢を1日の中で使い分けることが最大の予防策。
赤ちゃんの授乳リズムと乳腺炎予防
赤ちゃんのリズムは月齢によって変わります。
生後0〜1か月
- 1日8〜12回授乳(約2〜3時間ごと)
- 吸啜反射が強く、まだリズムは安定しません
- 夜間授乳も必要
生後2〜3か月
- 授乳回数は7〜8回程度に落ち着く
- 1回の飲む量が増える
- 夜のまとまった睡眠が出始める
生後4〜6か月
- 授乳は5〜6回程度
- 昼夜のリズムが安定し、夜間授乳が減る子も
- 離乳食が始まると徐々に授乳回数が減少
👉 授乳リズムが安定してくると、母乳が溜まりすぎるリスクが減り
乳腺炎予防にもつながります。
リズムを整えるポイント
- 「欲しがったら与える」スタンスを基本にしつつ、授乳間隔が空きすぎないよう注意
- 夜間授乳を嫌がらず、体調に合わせて対応
- 片側だけで終わらず、両方を交互に与える習慣を
受診の目安
- 悪寒・発熱・関節痛がある
- 胸のしこり部分が赤く熱を持つ
- 激しい痛みで授乳困難
→ この場合は早めに助産師や医師へ相談しましょう。
薬と漢方の活用
授乳中でも安心して使える薬
- ロキソニンなどの解熱鎮痛剤:授乳中も使用可能
- 葛根湯:体を温め、炎症を和らげる
葛根湯と「麻黄」
一般的な葛根湯には麻黄が含まれていますが、麻黄なしタイプの葛根湯も販売されています。
授乳中のママには、医師や薬剤師に相談しながら適したタイプを選ぶと安心です。
ママへのメッセー
「少し休めていますか?」
授乳も育児も、本当に大仕事。乳腺炎は「ママの体を休めてね」というサインかもしれません。
セルフケアと早めの相談でしっかり回復できます。
どうか無理せず、家族や専門家のサポートを受けながら、安心して母乳育児を続けてください。
母は本当に偉大です。今日もお疲れさまです🤍
まとめ
- 乳腺炎は母乳の滞りから突然起こる
- 前兆サインを早めにキャッチすることが重要
- 水分補給・休養・授乳姿勢の工夫が予防のカギ
- 赤ちゃんの授乳リズムを整えることも大切
- 薬や葛根湯(麻黄なしタイプもあり)を安心して活用できる
- 強い症状が出たら早めに受診
関連記事もあわせてご覧ください👇
- 👉 母乳量を増やすには?完母を目指すママのための7つの近道
母乳の出を良くするための生活習慣・食事・授乳の工夫を、助産師目線でまとめています。 - 👉 赤ちゃんの授乳リズムはいつ整う?月齢別の目安と整え方
新生児から6か月ごろまでのリズムの変化と、乳腺炎予防にもつながる授乳間隔の工夫を解説。